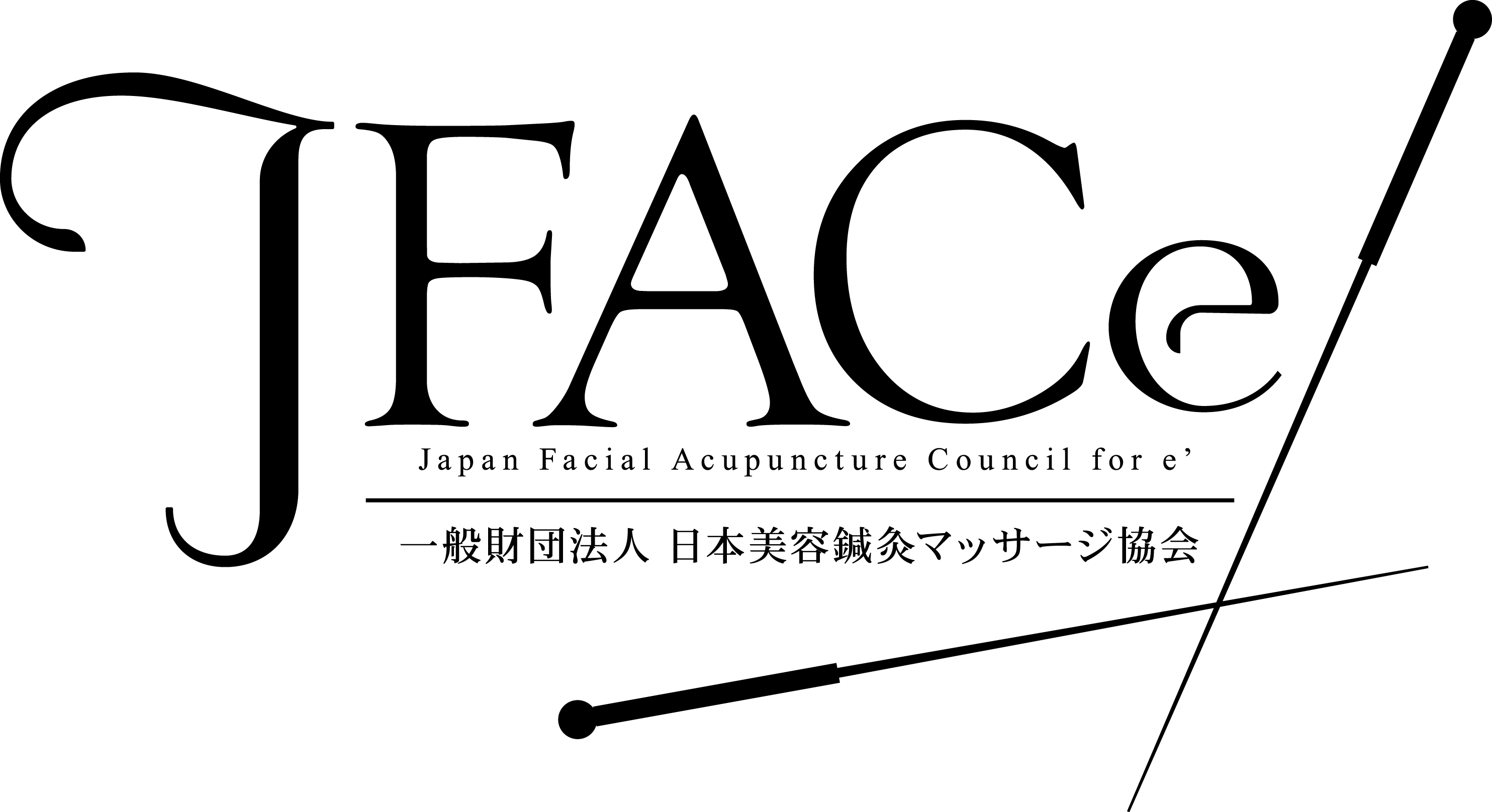こんにちは!
JFACe公認、美容鍼灸認定講師の井上堅介です。
<鼻の周り>や<眉間>、<頬>などの
顔の中心に近いところに『ニキビ』が出来てしまうと、
目立ってしまうので、他の人の視線が気になって嫌ですよね。

『ニキビ』が出来る場所と内臓の関係とは?
西洋医学的に考えると、
鼻の主な役割は、外界から空気(酸素)を取り込む窓口であると同時に、
体内に溜まった二酸化炭素を排出する呼吸器官の1つと考えられています。
そのために、
呼吸器官の代表者である『肺』と<鼻>には密接な関係があるのは誰もが予想できると思いますが、
中国医学的に考えた場合、
<鼻>だけではなく、<鼻の周り>や<眉間>、<頬>を含めた広い範囲が『肺』と密接な関係があると考えられています。
そのために、
鼻の周りや眉間、頬に『ニキビ』が出来るのは、
『肺』が何らかの原因で弱くなっていたり、機能が低下しているために、
ニキビが出来やすくなっていると考えられるんです!
中国医学的な『肺』の働きとは?
中国医学で考える『肺』の働きには、
① 外界から<清気>を取り込み、<濁気>を体外へ排出する
大気から清らかな気を体内に取り入れて、体内の老廃物を含んだ<濁気>を体外へ排出する働きを行います。
② 『津液(しんえき)』を体の隅々まで運ぶ
中国医学では、リンパや細胞間液などの血液以外の体液成分を『津液(しんえき)』と呼び、
『肺』は、この『津液』を体の隅々まで循環させる水分代謝機能を司っていると考えれています。
また、
汗の排出に関わる汗腺機能や皮膚の免疫機能にも関係があると考えられています。
肺とニキビの関係とは?
このように、
『肺』は常に外界との接触を頻繁に行う立場にあるために、
自然界にある<風邪>や<熱邪>などの病気の原因となる『邪気』を取り込んでしまう可能性があります。
その結果、
『肺』が『邪気』を取り込むことによって<熱>を持ってしまうと、
肺に溜まった熱や邪気を体外に排出しようとして、
<鼻の周り>や<眉間>、<頬>にニキビが出来やすくなってしまうんです!
その他にも、
雨天などが続き、外界の<湿邪>が『肺』に侵入してしまうと、
肺の水分代謝機能が低下してしまい、
体内に滞った水分である<痰>が形成されてしまい、肺が『湿熱』を帯びてしまうと、
湿熱を体外に排出しようとしてニキビが出来やすくなってしまいます。
肺の熱を取り去る方法とは?
このように、肺が邪気に犯されることによって熱を帯びてしまうことが原因で、
鼻の周りや眉間、頬にニキビが出来やすくなってしまうのですが、
ニキビを治すためにも、
原因となっている肺の熱を取り去るためにはどうしたら良いのでしょうか?
自分で内臓の調子を整える(肺の熱を取り去る)ためには、
医食同源の考え方から、薬膳という文化を生み出した中国では、
食べ物によって、
内臓のバランスを整える方法をよく取り入れます。
ちなみに、
今回のように肺の熱を取り去るのに適した食材は『梨(ナシ)』なんです!
梨(ナシ)の効能は、
『肺を潤して痰を切り、熱を冷まして体液成分を生む』
という効果があるので、
邪気によって肺に溜まった熱を取り去るのにピッタリですね。
その他にも、
ビワの葉茶も痰を除去して肺熱を取ってくれる効果があるので、
このタイプのニキビに有効ですよ!